
探偵業法の目的(一部抜粋)
探偵業者が業務を適正に行うため、また、他者の権利利益を保護するための法律が、「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。
探偵業法は、2006年5月25日に衆議院で可決され、同年6月2日に参議院も可決して成立し、同年月8日に公布され、2007年6月1日に施行されました。以下の内容があります。
未成年・懲役などを受けた後、期間が満たない人による調査は違法
探偵業法には、探偵業を行う上での様々な規制が記されています。
規制の一つが、探偵業を行う人について。
探偵になるには定められた国家資格は必要ありません。
自分で探偵と名乗ることはだれでも出来てしまいます。
業法ではこういった人が探偵になれるとは決められていませんが
探偵になれない人については記されております。
●第三条の概要
以下の要項に該当する者は、探偵業務を行ってはならない。
●未成年者
●刑事・行政処罰の経験がある者
(禁錮以上の刑を受け、刑の執行から5年経過しない者)
●探偵業法で定める第十五条による処分、違反をした者
●反社会的組織の構成員
●反社会的組織の構成員を辞めてから5年経過しない者
つまり、未成年者、一定の懲役などを受け期間が満たない人
などが探偵業を行うことは違法であるとされています。
さらに、第六条にて、調査の目的でも、人々の生活の平穏を阻害することはしてはいけないと述べられています。
●第六条の概要
探偵業務を行う者は、探偵業法またはその他の法令や条例で禁止された行為を使って調査を行うことは出来ない。
また、一般生活を送る人々の平穏な暮らしを乱したり、他人の権利利益を侵す行為を禁止する。
そのため、探偵に依頼したからすべてを調べてくれるだろう、と考えるのは早計です。
個人の権利や利益を侵害することは法律で禁じられています。
そのため、たとえば差別につながる事柄や懲役を受けたことがあるなどの情報を調べ、報告することは法律違反にあたるのです。
探偵業を通じて得た情報は漏らしてはならない
探偵に依頼するとき、「情報が漏れてしまうのではないか?」と心配される方はたくさんいらっしゃると思います。
●偵業法第十条の概要
探偵は調査で知り得た情報を依頼者以外の第三者に漏らしてはならない。
また、探偵業を辞めた者も同じ。
探偵は調査によって作成した資料などを不正・不当行為に利用してはならない。
また、探偵はそれらの資料を不正・不当行為に使われないよう対策を取る。
探偵業を廃業したあとでも、秘密をもらすことは法律違反となります。
また反対に業法により行ってもよいことが明記されています。
●第二条の概要
探偵業務とは、特定人の所在または行動を調べる業務のこと。
面接や聞き込み、尾行、張り込みなどの方法によってのみ業務が行える。
業務の内容は、調査の依頼者に報告する義務がある。
私達探偵が行えることは正直これだけです。
上記の6条と2条を見比べると一瞬??となりますがそこが探偵に許された範囲なのです。これらいがいにも日本国憲法ほどは多くはありませんが20%ほどの法律が探偵にはかせられているのです。
いっけん探偵なんて簡単だろ!とおもわれるかもしれませんが法を順守し違法行為とならない為の知識はかなり複雑に入り組んでおります。
探偵業法の一部ではありますが普段、探偵以外は気にかけない条例ですので記載させていただきました。
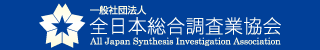
.jpg)